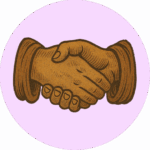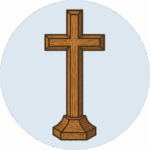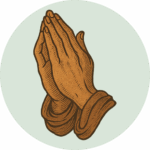ようこそ、自由と友愛の独立アングリカン教会へ
主の平和と祝福が、あなたとともにありますように。
このたびは、自由と友愛の独立アングリカン教会(The Independent Anglican Church of Liberty and Fellowship)のホームページを訪れてくださったことを、心より感謝申し上げます。
私たちの教会は、すべての人に開かれた、祈りと信頼の共同体です。カンタベリーと制度的結合を持たない独立聖公会として、アングリカン(聖公会)の霊的伝統に誠実に立ちつつ、開かれた交わりを大切にしています。誰ひとりとして退けられることなく、それぞれの歩みに寄り添いながら、神の愛のうちに生きる道を、ともに探し求めています。
ここで語られる「コイノニア(koinonia)」は、単なる集まりではありません。それは、聖霊によって結ばれた、深く静かな交わり—神と人、人と人とが、祈りと聖言のうちに結び合わされ、喜びも痛みも、隔てなく分かち合う、霊的なきずなのことです。
「自由(Liberty)」と「友愛(Fellowship)」、そしてキリストの福音に根ざして、私たちはこの現代社会という複雑で揺れ動く時代においても、誠実に祈り、耳を傾け、行動しながら、信仰の歩みを深めてまいります。
その歩みの核心にあるのが、「リベラル・アングリカニズム(Liberal Anglicanism)」の精神です。これは、アングリカン(聖公会)の豊かな典礼と伝統を重んじつつも、理性・聖書・経験という三重の信仰理解を尊重し、人間の尊厳と多様性、社会的責任と希望を中心に据える霊的姿勢です。
どうかこの小さな場が、あなたにとっても、主にある慰めと希望を見いだす場所となりますように。
新着情報とお知らせ
- 降誕日 説教草稿「言(ことば)が肉となった世界で、なお生きるために」言(ことば)が肉となった世界で、なお生きるために 【教会暦】降誕日 【聖書日課】旧約 イザヤ書 52:7-10使徒書 ヘブライ人への手紙 1:1-12福音書 ヨハネによる福音書 1:1-14 【本 文】 降誕日を迎え、私 […]
- 聖歌 82番「み使いの主なるおおきみ」
- 降臨節第4主日 説教草稿 「恐れのただ中で生まれる神」恐れのただ中で生まれる神 【教会暦】降臨節第4主日 2025年12月21日 A年 【聖書日課】旧約 イザヤ書 7:10-17使徒書 ローマの信徒への手紙 1:1-7福音書 マタイによる福音書 1:18-25 【本 文】 […]
- 教会時論 2025/12/13「核の言葉を慎め」核の言葉を慎め 官邸中枢から放たれた核保有発言は、抑止ではなく不信を生む。被爆国日本が踏み外してはならない一線は、すでに明白である。 2025年12月18日、首相官邸で安全保障政策を担う政府高官が、非公式取材に対し「日 […]
- 降臨節第3主日 説教草稿「揺れる問いのただ中で、来たり給う主を待つ」揺れる問いのただ中で、来たり給う主を待つ 【教会暦】降臨節 第3主日 2025/12/14 【聖書日課】旧約 イザヤ書 35:1-10使徒書 ヤコブの手紙 5:7-10福音書 マタイによる福音書 11:2-11 【本 文 […]
- 教会時論 2025/12/13「監視国家への坂道を止めよ」監視国家への坂道を止めよ スパイ防止法という名で、民主社会の基盤が静かに削られようとしている。安全保障の名目で自由を差し出すことは、決して中立な選択ではない。 高市政権は2025年内の検討開始を掲げ、いわゆるスパイ防止 […]
宣言と声明

自由と友愛の独立アングリカン教会の信仰の三色旗
この旗は、自由・友愛・独立という三つの霊的価値を、三色と三段の構成によって表しています。
上段の灰青色は、神の真理に導かれる霊的自由を、中央のローズグレーは、祈りと交わりに宿る温かな友愛を、下段のダークシダーは、御前に誠実に立つ自立と責任を象徴します。三段の構造は、天に向かう志、中ほどで結ばれる交わり、地に堅く立つ信仰の歩みを形づくっています。
この旗は、目に見えるしるしとして、私たちの霊性の深みに祈りを響かせるものです。
リベラル・アングリカニズムに根ざした、すべての人のための教会
カトリックにしてアングリカン
— 公同の信仰と改革の伝統に生きる教会
「あなたがたは、選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それは、あなたがたを闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある業を、あなたがたが広く伝えるためなのです。」
— ペトロの手紙一 2章9節
自由と友愛の独立アングリカン教会は、英国国教会(The Church of England)において培われてきた信仰と礼拝の伝統を、今も尊び、誠実に受け継ぐカトリック(公同)にしてアングリカン(聖公会)の教会です。私たちは、キリストにある普遍の教会の一部として、時代のただ中にあっても、福音の光に照らされて歩むよう招かれています。
私たちは制度上、アングリカン・コミュニオン(The Anglican Communion)という組織体には属していませんが、アングリカンの神学の深みと典礼の豊かさ—すなわち、祈りとともに代々受け継がれてきた霊的な知恵と営み—を変わらず大切に守り続けています。
この伝統の根幹には、聖書への謙虚な信頼と、三信条—すなわちニケア信条・使徒信条・アタナシウス信条—への確かな信仰告白があります。さらに、聖霊の導きのもとに連綿と受け継がれてきた聖職の系譜(使徒継承)も、私たちの教会のいのちを支える欠くことのできない柱です。
本教会の典礼は『公祈祷書』(The Book of Common Prayer、以下 BCP)に基づいており、その中でも1662年版(BCP1662)を正式な典礼基準として採用しています。その一言一言には、神を仰ぎつつ歩む者の沈黙と祈りが息づいており、日々の信仰を養い、励ます力があります。
とはいえ、私たちは伝統を「保守」としてではなく、「希望」として受けとめています。たんに制度や形式にとどまることなく、つねに問い、悔い改め、新たにされつづけること—それこそが、私たちが大切にする改革の霊です。「誠実とは何か」「自由とはいかなる恵みか」と問うことをやめず、神の御前に真実に生きようとする姿勢こそが、私たちの祈りです。
この信仰理解と教会のかたちを貫くのが、リベラル・アングリカニズムです。
それは、聖書と理性と経験に誠実に向き合い、多様な声に耳を傾けつつ、祈りと共感に満ちた共同体を形成しようとする霊的志向です。私たちは、この開かれたアングリカン(聖公会)の伝統こそが、今の時代にふさわしい福音の器であると信じています。
すべての人に開かれた、神の愛に生きる交わり
隣人を自分のように愛しなさい。」
— マタイによる福音書 第二十二章三十九節
主イエス・キリストのこの御言葉に導かれて、私たちは、あらゆる境遇と背景を越えて、すべての人を神の愛のうちに受け入れる信仰の交わり(コイノニア)として歩むことを願っています。
性別や年齢、国籍や文化、性的指向、信仰の歩みにおける多様な経験を尊重し、聖なる交わりは、あらゆる隔ての壁を越えた包摂的で開かれた空間のうちにこそ息づくと信じています。そこでは、祈りと赦し、そして癒やしがともに分かち合われ、誰もが安らぎのうちに身を置くことができる—そのような信仰共同体を、私たちは目指しています。
この交わりに、入会の条件や資格はいりません。信仰とは、神の無償の恵みにこたえる応答としての歩みであり、教会はその道をともにする場です。
私たちが掲げるリベラル・アングリカニズムの精神に基づくこの開かれた姿勢は、教義や立場の一致よりも、他者を尊重し合い、希望と痛みを分かち合う生きた関係を大切にするところに根ざしています。
神は、過去によってではなく、今を生きるあなたに語りかけておられます。その呼びかけに耳を傾け、ご自身をそのままに受け入れ、ともに神の道を歩んでまいりましょう。交わりとは、正しさの証明ではなく、いのちを喜び、支え合う旅なのです。
礼拝と祈り、信仰を育む日々の歩み
「キリストの言葉があなたがたのうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、感謝の心をもって詩編と賛歌と霊的な歌を神に向かって歌いなさい。」
— コロサイの信徒への手紙 3章16節
私たちの礼拝は、アングリカンの典礼伝統に深く根ざしており、1662年版『公祈祷書』の精神に基づいて捧げられています。そこに息づく祈りの言葉は、幾世代にもわたり聖徒たちの口にのぼり、いまもなお神へのまごころを形づくる霊的遺産として受け継がれています。
聖書朗読には、『聖書 新共同訳』または『聖書協会共同訳』を用いています。朗読される御言葉は、古の預言者たちの証しであると同時に、今を生きる私たちに語りかける主イエス・キリストの生ける声として、心の深みへと光を投げかけます。
礼拝の中心には、聖書朗読と説教、信仰の告白、とりなしの祈り、平和のあいさつ、そして主の聖餐があります。これらは単なる儀式ではなく、神の現存にあずかる、深く霊的な交わりの時です。
祈りとは、義務や習慣ではなく、神の呼びかけに対する魂の応答です。疲れた者は慰めを得、打ち砕かれた者はいやされ、新たな力と希望が静かに注がれる—そのような恵みの時が、礼拝のうちに満ちています。
私たちは、この礼拝をリベラル・アングリカニズムの精神とともにささげています。すなわち、形式の厳格さの中にも柔らかな包容力が息づき、祈る者一人ひとりが、自らの良心と理解に基づいて神に向かうことができるような、深く開かれた霊的空間を大切にしています。
信仰が日々の歩みに根づき、祈りが呼吸のように自然に響き渡るようになること—それは、私たちが互いに支え合いながら目指している霊的な旅路です。
この礼拝は、すべての人に開かれています。信仰の深さにかかわらず、求める心をもってどうぞお越しください。あなた自身の歩みにふさわしい仕方で、私たちと共に祈り、神の招きに応えていただけたら幸いです。
使徒継承とともに歩む聖職のかたち
「人々は彼らの上に手を置いて祈り、任命した。」
— 使徒言行録6章6節
教会における聖職の起源は、主イエス・キリストご自身が選び召された使徒たちにさかのぼります。彼らに託された奉仕の務めは、祈りと按手をもって世代を超えて継承され、今日に至るまで、教会の霊的な生命線として脈々と保たれてきました。
この「使徒継承(Apostolic Succession)」とは、単なる歴史的・制度的な継続を意味するものではありません。それは、神のことばに仕え、祈りと聖奠(the Sacraments)をもって神の民を養い、教会の交わりと一致を支えるという、深い霊的召命への応答のしるしです。聖職者は、キリストの体なる教会にあって「共に仕える者」として立てられ、祈りのうちに民とともに歩み、その信仰と生活を支える奉仕に生きる者です。
この召命は、性別や性自認を問わず、神の招きに応えるすべての者に開かれています。聖職按手は、教会の識別と祈りのうちに正当に授けられ、使徒継承に連なる恵みとして、すべての時代の教会に与えられています。
私たちの教会は、主教(Bishop)、司祭(Priest)、執事(Deacon)の三つの職務を重んじます。それぞれは固有の賜物と使命を携え、教会に仕えます。主教は使徒的信仰と教会の一致の担保として、司祭は御言葉と聖奠をもって共同体を養う牧者として、そして執事は奉仕の務めにおいて主の謙遜と愛を体現する者として立てられています。
このような聖職のかたちは、時代や文化を超えて、教会が神の恵みに応えて生きるために与えられた「かたち」であり、特権としてではなく、奉仕として謙虚に、誠実に担われるべき召命です。聖職とは、神の前において特別にされた存在であるがゆえに、むしろ深く仕える者として招かれている—その事実を、私たちは心に刻みます。
使徒たちの祈りと按手に始まるこの霊的継承は、いまを生きる教会にとって、過去から未来へと続く信仰の架け橋であり、神の忠実さを証しするしるしです。私たちはこの恵みの中にあって、与えられた奉仕に忠実であり続けたいと願います。
教会のかたち:三つの柱に生きるキリストの体
「あなたがたは、キリストの体であり、また、一人一人はその部分です。」
— コリントの信徒への手紙一 12章27節
福音に仕える三つの柱
自由と友愛の独立アングリカン教会は、現代という裂かれた時代において、福音に忠実な教会のかたちを祈り求め続けています。その中核に据えられているのが、「ディアスポラ教区」、「十字架と復活の教区」、そして「福音的自律聖職運動」という三つの柱です。
これら三つは、単なる制度的構想ではありません。むしろそれぞれが、異なる次元における霊的応答のかたちであり、相互に補い合いながら、一つのキリストの体としての教会共同体を形づくるものです。
ディアスポラ教区
— 散らされた場所における陪餐のかたち
「ディアスポラ教区(The Diocese of the Diaspora)」とは、国境や制度、建物や教勢といった外的条件に縛られることなく、どこにあってもキリストの食卓にあずかることを可能にする、陪餐共同体の器です。
空間的・制度的制約を超えて祈りと聖奠にあずかるこの構造は、主の体に結ばれた者たちが、どこにいても「共に在る」という交わり(コイノニア)を具体化する、柔軟かつ霊的に深い教会のかたちです。
そこでは、BCPに則る礼拝、使徒的継承に基づく主教職、信徒の主体的参与が一体となって、「どこにいても神の国を共に生きる」福音的共同体が築かれています。
このディアスポラ的礼拝生活を支える典礼の中核として、「アンテ・コミュニオン(Ante-Communion)」の形式が豊かに用いられています。こうした礼拝共同体は、「聖餐前小教会」と呼ばれ、小規模であっても主の日ごとの祈りを守り続けています。
アンテ・コミュニオンとは、BCP1662に基づく、陪餐前の整えられた礼拝構造を指します。ただの「省略」ではなく、御言葉と祈りに根ざした正統な公祈祷であり、陪餐がかなわない時にも主の臨在にあずかり、交わりを育む霊的奉仕のかたちです。
自由と友愛の独立アングリカン教会では、認可を受けた補祭 伝道師が主教の監督のもと、「聖餐前小教会」においてアンテ・コミュニオンを執り行うことが制度的に認められており、小規模な会衆や司祭不在の地域でも主日礼拝が守られ、共同体としての一致が支えられています。
御言葉の朗読、信仰告白、赦しと祈願を通して、信徒は神の語りかけに応答し、「聖言における陪餐(Communion in the Word)」の霊的現実に生きることができます。これは、神の臨在は聖餐に限られず、御言葉と祈りのうちにも確かに顕されるというアングリカン(聖公会)の典礼神学に根ざした理解です。
アンテ・コミュニオンは、単なる代替ではなく、今日あらためて照らされる霊的資源として、「聖餐前小教会」における礼拝生活の中心を担っています。どこにあっても、ともに祈る教会の姿を実現する道なのです。
十字架と復活の教区
— 裂かれた世界への霊的応答
「十字架と復活の教区」は、教会が歴史の痛み、差別、分断、喪失のただ中でいかに福音を生きるかという問いに、祈りと証しのうちに応える霊的共同体です。
この教区の召命は、「主のからだとして裂かれることを恐れず、復活の希望に生きる」という、十字架と復活の神秘に深く根ざしたものです。
難民、孤立、孤独死、ジェンダー差別、環境破壊、戦争といった現代の断絶に向き合うとき、教会は沈黙せず、むしろその裂け目のただ中にキリストの痛みと光を証しする存在として立つことが求められます。
この教区は、典礼的にはディアスポラ教区と密接に連携しつつ、社会的実践・公共神学・霊的介入の場として、その預言的使命を担っています。
福音的自律聖職運動
— 仕える者としての召命
「福音的自律聖職運動」は、制度に依存せず、財的保障に頼らず、日常の労働と祈りのなかで聖職を生きる者たちの共同の霊的証しです。
彼らは、信徒と同じ場所で働き、生き、悩み、そして同じテーブルでパンを裂くことによって、キリストの体に仕えるという聖職の本質を、文字通り自らのからだで生き抜いています。
この運動は、制度の外側から制度を刷新し、聖職者が清貧・無名・無償のうちに仕えることこそが、福音にふさわしい生き方であることを、静かに、しかし確かに証しします。
彼らの召命は、「奉仕は聖なる務めであり、聖職は生きられた祈りである」という真理に貫かれています。
相補的な交差と、一つの体としての教会
これら三つの柱—ディアスポラ教区・十字架と復活の教区・福音的自律聖職運動は、それぞれが異なる方向から教会の霊的実在を形づくりながら、互いを照らし合い、補完し合う関係にあります。
▪︎ ディアスポラ教区
礼拝と聖奠による陪餐の広がりを生み出し、
▪︎ 十字架と復活の教区
社会的痛みに対する教会の預言的応答を担い、
▪︎ 福音的自律聖職運動
聖職の霊性と労働を架橋する奉仕の現場を開きます。
三つの柱が織りなすこの構造は、単なる戦略的な制度設計ではありません。
それは、教会がキリストの体として、裂かれ、仕え、集う存在であるという霊的本質を、具体的に証しする働きなのです。
私たちは、こうした多元的な教会の形にこそ、リベラル・アングリカニズムの精神が最も力強く息づいていると信じます。すなわち、固定化された教会像を超え、神の愛の多様なかたちに開かれ、常に新たにされていく柔軟性と責任、そこにこそ、現代における福音のいのちがあります。
現代社会への神学的なまなざしと応答
「私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリスト・イエスにおいて造られたのです。」
— エフェソの信徒への手紙 2章10節
この創造の御業に立ち返るとき、私たちはすべての人が尊厳と自由と平等のうちに創られたことを深く思い起こします。信仰とは、ただ過去の真理を護る営みではありません。それは、いまこの時代の痛みと叫びに、福音の光をもって応答していく生きた責任でもあります。
ジェンダーの多様性、気候危機、経済格差、社会的不正義――
これら現代的課題に沈黙することは、もはや福音の精神に忠実とは言えません。
私たちは、創造主のまなざしを受け継ぐ者として、神が造られた世界とそこに生きる隣人に対して霊的・倫理的に誠実であることを求められています。
この霊的姿勢は、私たちが掲げるリベラル・アングリカニズムの神学的基盤と深く結びついています。すなわち、信仰の内実は、個人の救済や神秘にとどまるものではなく、社会と歴史に向かって開かれた行動の責任でもあります。
また、神が創造された人間の関係の中で、互いに誠実と愛に生きる結びつきは、性別や性自認にかかわらず、聖婚(Holy Matrimony)として教会の祈りのうちに祝福されるべきものです。本教会は、同性間の結婚をも神の召しと愛に応える交わりとして、当然のごとく受け入れ、聖なる結合として承認し、祝福いたします。
「神がお造りになったものは、すべて良いものである。」
— テモテへの手紙一 4章4節
この御言葉は、創造の全体が神の善なる意志に貫かれているという信仰の核心を、私たちに思い起こさせます。
世界を守ること、隣人の尊厳を守ること、そして真理に対して誠実であること――
これらすべてが、私たちの祈りであり、信仰の実践なのです。
私たちはこの責務を、開かれた神学(Open Theology)として祈りと共に担っていきます。
伝統への敬意を失わずに、しかし変わりゆく現実のなかで、つねに「問い」「聴き」「応答する」こと。
それこそが、リベラル・アングリカニズムにおいて信仰が生きる場なのです。
教会は、壁に囲まれた礼拝堂の中だけにあるものではありません。
むしろこの世界こそ、神の創造として見つめ直すべき祈りの場であり、応答の場です。
私たちはそこにおいて、不断に問い、祈り、従っていく交わりであり続けたいと願っています。
信仰と理性が響き合う、祈りと対話の共同体
「愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に堅く結ばれなさい。互いに兄弟愛をもって愛し合い、互いに敬意をもって相手を優れた者としなさい。」
— ローマの信徒への手紙 第12章9〜10節
信仰と理性は、決して対立するものではありません。むしろそれは、いずれも神から与えられた賜物であり、互いに照らし合いながら、私たちを真理へと導く光です。疑問を抱くこと、思索を重ねること、異なる意見に耳を傾けること—それらすべてが、私たちの信仰の成熟をうながす「祈りのかたち」なのです。
祈りと学び、直感と思索、実践と黙想—
これらの営みは、信仰生活の呼吸であり、神との交わりを日ごとに生きるための霊的なリズムです。
私たちは、知を軽んじることなく、また理屈に偏ることなく、知的誠実さと霊的深さとを共に大切にする信仰共同体でありたいと願っています。問いを抱くことを恐れず、沈黙に耳を澄ませ、異なる声に敬意を払いながら、自由に探究し、誠実に問い、信じる道を、共に歩んでまいります。
この姿勢の背後にあるのが、リベラル・アングリカニズムの対話的神学です。それは、真理を単一の命題に閉じ込めるのではなく、複数の経験と視点が交差するところに、神の臨在を見いだす神学です。
この歩みは、孤独な旅ではありません。祈りと対話の交わり—すなわちコイノニア—に支えられ、神の民として共に育まれていく旅路です。
学びは、ただ知識を積む営みにとどまらず、神と人とに向き合い、人生の深みにある問いに応える、祈りのかたちのひとつでもあります。
そこには、神の知恵と憐れみが、静かに、しかし確かに息づいているのです。
あなたをお迎えする教会として
「疲れた者、重荷を負う者は、だれでも私のもとに来なさい。私があなたがたを休ませてあげよう。」
— マタイによる福音書 第十一章二十八節
自由と友愛の独立アングリカン教会は、祈りと赦し、そして希望に満ちた信仰の交わりとして、すべての人に開かれた聖なる空間でありたいと願っています。
ここでは、誰もが自らの声で祈り、それぞれの歩調で、神のもとへと近づくことが許されています。
信仰とは、一定の理解や確信を有することではなく、「いま、ここにあるあなた」が、神のまなざしのもとに大切にされているという現実に気づくことから始まります。
もしあなたが、信仰に対する戸惑いの中にあっても、あるいは言葉にならない問いや葛藤を抱えていたとしても、それを恥じる必要はありません。
神は、問いの沈黙にも、涙と喜びのすべてにも、ともにおられます。
信仰の旅路には、それぞれ異なるリズムがあります。
だからこそ、私たちは、いついかなる時にも、変わることのないまなざしと心で、あなたをお迎えしたいのです。
どうか、あなたの魂が静かに立ち止まりたくなったときに、この教会の扉を開いてみてください。
どのようなかたちでも構いません。その一歩が、あなたにとっての祝福となるよう、私たちは祈りながら待っています。
リベラル・アングリカニズムに基づくこの開かれた教会は、問いを抱く者も、確信に満ちた者も、道に迷う者も、すべての人を主にある兄弟姉妹として迎え入れます。
あなたという存在が、この交わりに新たな光をもたらしてくださると、心から信じています。
日本聖公会とのつながり
自由と友愛の独立アングリカン教会は、アングリカンの神学と礼拝の伝統に忠実に立ちながら、独立した信仰共同体としての歩みを続けています。
制度上、日本聖公会(The Nippon Sei Ko Kai)とは異なる構造を有していますが、私たちは、同じアングリカン(聖公会)の霊的遺産をともに受け継ぐ者として、深い敬意と連帯の思いを抱いています。
三信条に根ざした信仰、BCPに基づく典礼、そして神の国の実現をこの世において求めていく志—
これらの点において、私たちは確かに、日本聖公会と同じ流れに連なる者であると確信しています。
制度や形式の違いにとらわれることなく、キリストの体の一員として互いを尊び合うこと。
それこそが、アングリカン(聖公会)の「中道の精神(via media)」に脈打つ、普遍的な霊性であると、私たちは信じています。
ゆえに、祈りと敬意をもって、キリストにある兄弟姉妹としての交わりを、これからも謙遜に、そして誠実に育んでいきたいと願っています。
この文章に目をとめてくださったあなたに、
心より感謝申し上げます
これまでどのような道を歩んでこられたとしても、あるいはいま、どのような場所に立っておられたとしても、神の愛はすでにあなたを包み、やさしく招き、導こうとしておられます。
信仰の第一歩を踏み出すときにも、立ち止まり、静けさのうちに祈りを深めたいと願うときにも、どうか、この小さな交わりのことを思い出してください。
私たちの教会は、あなたをお迎えする場であり、共に祈り、共に悩み、共に神の国を志す共同体でありたいと願っています。
どうか、あなたの声を、問いを、沈黙さえも、隠すことなく差し出してください。
それは、神にとって、そして私たちにとっても、かけがえのない賜物なのです。